車を長く安全に乗り続けるためには、定期的なメンテナンスが大切です。
しかし、「メンテナンス」と聞くと専門の整備工場に頼まなければいけないと考えてしまう方も多いでしょう。実際のところ、基本的なメンテナンスであれば初心者でも簡単にできるものが少なくありません。
今回は、メンテナンスの種類や自分でできる作業について分かりやすくご紹介します。車を持ち始めたばかりの方はぜひ参考にしてみてください。
車のメンテナンスは初心者でもできる!

車を長く安全に乗るためには、メンテナンスが不可欠です。しかし、メンテナンスと聞くと、専門業者に頼まないといけないと思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、基本的なメンテナンスであれば、初心者でもできるものが多いといわれています。
今回はメンテナンスの種類や、初心者でもできるメンテナンス項目について解説します。自家用車を持ち始めて間もない方はぜひ参考にしてください。
車のメンテナンスが重要な理由
そもそも、なぜ車のメンテナンスが重要なのでしょうか。理由は主に2つあります。
1つ目は、定期的にメンテナンスをすることで車の安全性を高められるためです。ブレーキがかかりにくくなっていないか、タイヤがすり減っていないかなどを確認できるため、故障や事故のリスクを減らせます。もし、メンテナンスの時点で異変があれば、修理もしくはパーツ交換することで安全性を高められます。
2つ目は、大きな修理によるコストの増加を防げるからです。メンテナンスをしないまま修理をするとあちこちに不備が生じて修理が大掛かりになる可能性があります。
車のメンテナンスは主に2種類

車のメンテナンスといっても、大きく分けて2種類あります。それぞれが持つ意味や役割は異なるため、使い分けをすることで、車の寿命をより長くできるでしょう。
ここでは、メンテナンスの種類について解説します。
自家用車を持っていると、「定期点検」や「○ヵ月点検」に関するお知らせのハガキが届いた経験があるはずです。これらは「定期点検整備」と呼ばれ、自動車が故障しないように、性能が維持できているか確認または予防するための点検です。人間でいうと「健康診断」が最も近い例えといえます。
定期点検は、1年点検や2年点検など、定められた期間ごと実施することが義務づけられています。定期点検は原則使用者が行うのですが、点検項目は複雑で、機械整備のプロにしか分からないものが多く、項目によっては分解作業も必要です。
そのため、ほとんどの場合、ディーラーなどの認証整備工場や指定整備工場(民間車検場)に委託するケースがほとんどです。
日常点検とは、車の保有者でもできる点検のことです。この点検は定期点検とは異なり、義務ではなく、走行距離や運行時の状態などから判断し、適切な時期に実施します。
ただし、バスの運転手やタクシーの運転手、トラックの運転手などは毎日安全に走行できるよう、一日一回、必ず走行前に日常点検を実施してください。なぜなら、これらに携わる車は、公共性が高く、万が一事故や故障が起きたとき、社会的影響が大きくなるためです。
日常点検を怠った結果、人や物を乗せた状態で故障すると、大きな事故につながりかねません。一般の人でもできるからといって侮れないのが日常点検です。
初心者でもできる車のメンテナンス項目
ここからは、初心者でもできる車のメンテナンス項目を15個解説します。
国土交通省によると、車の日常点検には大きく分けて「エンジンルーム」「車まわり」「運転席」の3ヵ所あり、そこから細かく枝分かれしています。
一見15項目と聞くと多いように感じるかもしれませんが、どれも簡単にできるものばかりです。ぜひ明日から、これらの項目を点検してみてください。

エンジンオイルの量は、エンジンがスムーズに稼働できるかを左右する重要な要素です。また、エンジン自体の寿命にも関わるため、こまめに点検しましょう。
点検方法は、まず平坦な場所に車を止めて、エンジンを切ってください。その後、ボンネットを開けて、オイルレベルゲージを抜き取ります。拭いてから再び差し込み、再度抜いたとき「F」(上限)と「L」(下限)の間にオイルがあればOKです。
万が一、エンジンオイルの量が不足した場合、エンジン自体の故障につながる可能性があるため、注意が必要です。エンジンオイルの量だけではなく、色や粘度も確認してください。なぜなら、エンジンオイルが黒ずんでいたり、ザラついていたりすると故障の原因になりかねないからです。もしオイルに異常を感じたら交換を依頼しましょう。
オイル量や質を適切に保つことで、エンジンの潤滑性能を維持し、故障のリスクを下げられます。
バッテリー液の量も日常点検における重要な項目の1つです。
点検方法は、エンジンルーム内にあるバッテリーの液量が「UPPER」と「LOWER」の間にあるか確認します。もし、不足していた場合、精製水を補充すればOKです。
ただし、メンテナンスフリーバッテリーが搭載された車は、バッテリー液の補充は不要です。そのため、事前にお持ちの車がどのタイプなのか確認しておきましょう。

ブレーキオイルの量も適切な量になっているか点検しておきましょう。
点検方法は、リザーバータンク内の液量が「MAX」と「MIN」の間にあればOKです。万が一、ブレーキオイルの量が適量より減っていると、液漏れやブレーキパッドが消耗している可能性があります。
あわせて、ブレーキ液の色も確認しておきましょう。新品は透明ですが、使用している期間が長くなると濁ったり、変色が進んだりと透明ではなくなります。
ブレーキオイルは各ブレーキに制動力を伝達するための、いわば核にあたる部分です。定期的に確認し、安全性を保ちましょう。
冷却水の量の確認も日常点検において重要です。
点検方法は、リザーバータンク内の水位を確認し「FULL」と「LOW」の間にあればOKです。もし、極端に減少している場合、冷却水が漏れ出している可能性があるため、早急に業者に点検を依頼しましょう。
早急に点検を依頼する理由は、冷却水不足はエンジンのオーバーヒートを招き、深刻な故障につながる恐れがあるからです。
冷却水を補充する際は、エンジンが冷えた状態にし、必ずメーカー指定の冷却水を使ってください。

ウインド・ウォッシャー液の液量確認も日常点検における重要な項目です。
点検方法は、エンジンルーム内のリザーバータンクを見て、液量が十分補填されているか目視するだけです。万が一不足していた場合、水もしくは専用の液を補充します。
特に北海道などの寒冷地では凍結防止のため、ウインド・ウォッシャー液が減りやすい傾向にあります。そのため、こまめに補充することで、いざというときに足りない事態を防げるのです。日々の安全運転のためにも必ず確認しましょう。
ここからは、車まわりの日常点検について解説します。
まずは、タイヤに亀裂やダメージがないか点検しましょう。点検方法は4本のタイヤに偏摩耗や傷、ひび割れがないか確認します。特に、偏摩耗は空気圧不足など様々な要因で生じるため、しっかりチェックしましょう。また、サイドウォールが十分に膨らんでいるかもあわせて確認してください。
タイヤは、安全性を高める重要な要素であるため、傷やひび割れの度合いによっては、パンクやバーストにつながる恐れがあります。運転中立ち往生するリスクを上げないためにも、こまめに確認することが大切です。
また、サイドウォール部分にコブのような膨らみがある場合、タイヤ内部が損傷している可能性が高いため、早急に交換を依頼しましょう。その他、釘やガラス片など、異物が混入していないかチェックすることも事故や故障防止につながります。
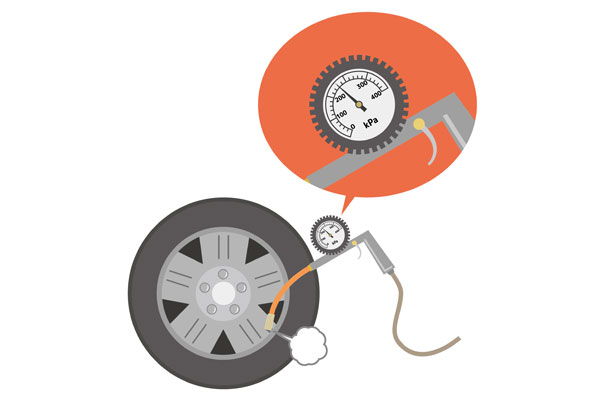
タイヤのダメージだけではなく、空気圧も大切な点検項目です。
点検方法は、エアゲージを用意して、適正空気圧になっているか確認します。運転席ドアの端やセンターピラーに適性空気圧が表示されているため、初心者でも確認できる項目です。
点検頻度は月に1回以上が目安です。気づいたときにこまめに点検し、パンク防止に努めましょう。
タイヤの空気圧は、タイヤが冷えている状態で行うのがポイントです。そのため、必ずエンジンを止めてしばらく経ってからか、エンジンをかける前に点検するのがおすすめです。
タイヤの空気圧が足りないと、走行にエネルギーが必要になるため、燃費が悪くなったり、偏摩耗を引き起こしたり、ハンドル操作が重くなったりと、様々なリスクを引き起こします。特に注意してほしい現象は「スタンディングウェーブ現象」です。
「スタンディングウェーブ現象」とは、タイヤの空気圧が不足した状態で高速走行をすると、タイヤがウェーブ状に変形してしまい、まともに走行もできなくなる現象です。そうならないためにも、こまめにタイヤの空気圧を点検してください。
タイヤのダメージ、空気圧とあわせて点検してほしいのがタイヤの残り溝の深さです。
点検方法は、タイヤ表面のスリップサインが出ていないか確認します。スリップサインとは、溝の深さが1.6mm以下になると現れる突起です。もし、スリップサインが1カ所でも出ていたら、タイヤ交換が必要になるため、タイヤ全体をくまなく確認しなくてはなりません。
スリップサインが出ていなくても、タイヤが摩耗してくるとハイドロプレーニング現象が起こりやすくなるため、注意が必要です。
スタッドレスタイヤの場合は、プラットホームと呼ばれる突起まで摩耗すると、交換時期にあたります。雪道を安全に走行するため、あわせて点検が必要です。
車まわりの点検はタイヤだけではありません。ランプ類の点灯・点滅やダメージも重要な点検項目です。
点検方法は、エンジンをかけて、ヘッドランプやテール・ランプ、ブレーキランプなど、全てのランプが問題なく点灯するか確認します。点灯するかどうかだけではなく、点滅速度も確認し、レンズに汚れや損傷がないかもあわせて確認しましょう。
万が一、ヘッドランプが点灯しない場合、暗い状況で走行するため、十分な視界が確保できません。さらに、ウインカーやブレーキランプに異変が生じていると、周囲に意思表示ができなくなり大変危険です。
ランプ類の電球切れは前兆がほとんどありません。そのため、小まめにチェックすることが安全性を維持する最も確実な方法です。
最後に運転席部分の日常点検項目について解説します。
まずは、エンジンのかかり具合に問題がないか、異音がないか点検しましょう。点検方法は、エンジンをかけたとき、スムーズにかかればOKです。このとき、普段と違う音がしないか、かかりにくさはないかなど、普段と違う点がないか必ず確認してください。
万が一、異変を感じた場合、燃料系統やエンジン内部にトラブルが生じている可能性があります。そのため、少しでも異変を感じたら専門業者に点検を依頼しましょう。

ブレーキペダルも大切な点検項目です。
点検方法は、エンジンを切り、ペダルをゆっくり踏み込んで、適切な踏み残しがあるか、正常な踏みごたえがあるか確認します。次に、エンジンをかけて走行し、ブレーキの効き具合が正常か確認しましょう。
万が一、踏み込みが柔らかかったり、効きが悪かったりした場合は、ブレーキ液が漏れ出しているか、空気が混入している可能性があります。そのため、異変を感じたら早急に専門業者へ点検および修理を依頼しましょう。
ブレーキペダルとあわせてパーキングブレーキも点検しましょう。
点検方法に関しては、レバー式の場合、引きしろが適切か確認し、ペダル式なら踏みしろを確認します。万が一引きしろまたは踏みしろが極端な場合、駐車時に思わぬトラブルに見舞われる可能性があるため注意が必要です。
ただし、電動パーキングブレーキを採用している車は、解説した点検方法とは異なります。そのため、事前に取扱説明書を確認し、適切な点検方法を実施しましょう。
エンジンのかかり方だけではなく、エンジンの低速・加速の状態も日常点検項目です。
点検方法は、まずエンジンが温まった状態で、アイドリング時の回転がスムーズかを確認します。次に、実際に走行してアクセルペダルをゆっくり踏み込んで、引っかかりがないか確認します。特に、加速時にはノッキングなどの異音や振動が発生する可能性があるため注意が必要です。
万が一異常が見られた場合、業者に点検を依頼しましょう。
ウインド・ウォッシャー液の噴射状態も、日常点検項目の1つです。運転中の視界確保に直結するため、こまめに確認しましょう。
点検方法は、運転席に座って実際にウォッシャー液を噴射します。フロントガラスへの噴射の向きと高さが適切であればOKです。万が一、噴射力が弱かったり、向きがおかしいと感じたりする場合、ノズルの詰まりもしくは調整不良の可能性があります。
フロントガラスの汚れを落とせないまま走行すると、視界不良により歩行者や障害物の確認が遅れ、事故を引き起こす原因になりかねません。

ワイパーの拭き取り状態を確認することも日常点検項目です。
点検方法は、レバーを操作し、低速と高速でワイパーを作動させます。吹き残しやムラ、ビビリなどの異常がなければOKです。万が一拭き取り状態が悪いと悪天候のときの視界不良による事故の危険性が高まるため注意が必要です。
ワイパーはゴムでできているため、どうしても劣化してしまいます。もし自分でワイパーを交換できない場合は、業者に交換を依頼しましょう。
初心者にはカーリースのメンテナンスパックが便利!

自分で日常点検するといっても、本当に確認できているかどうか不安に感じる方も多いでしょう。しかし、業者に点検や修理を依頼するとなると、どこに頼んだら良いか迷ってしまうのではないでしょうか。そこでおすすめしたいのが「カーリースのメンテナンスパック」です。
「カーリースのメンテナンスパック」は、車の部品交換や修理を定期的に行い、車両の安全性と快適性を維持するためのサービスです。
ここからは、カーリースのメンテナンスパックの特徴について解説します。
メンテナンスパックには定期点検が含まれているため、自分で点検する手間を省きながら、故障や事故のリスクを最小限に抑えられます。
メンテナンスパックに加入していなくても整備や点検を受けられますが、メンテナンスパックに加入していれば整備工場から必ず連絡がくるため忘れることもありません。
メンテナンスパックに加入すると、期間中は費用が発生しません。そのため、まとまった資金を用意する必要がないのも大きな特徴です。
本来であれば、オイル交換や定期点検など、都度メンテナンス費用がかかります。その点、カーリースであれば費用を抑えられるため、コストパフォーマンスが良いと加入者が増えてきています。
まとめ
カーリースに関してのエキスパート集団です。カーリースに関する様々な疑問にお答えしていきます。



